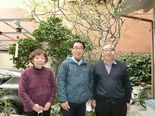「家のつくりようは夏をむねとすべし冬はいかなる所にも住まる。暑きころ わろき住居は堪えがたきことなり」 吉田 兼好
住まいのかたちは、その国の気候風土、自然環境によって決まってきます。日本の伝統的な木造住宅も日本の高温多湿の夏をいかに過ごせるかということに、重点が置かれて造られてきました。
開ければ、ひとつながりにの空間となる襖や障子、建具を閉めた状態でも通風が確保される欄間、冷たい空気を取入れる地窓、京町家に見られる夏になると、衣替えするシトミ戸(よしずなどを組み込んだ風通しのよい建具)、ガラリ戸、大きな開口部などによって、通風が確保されていました。
又、外部の熱・光の緩衝帯となる縁側、夏の高い位置にある直射日光をさえぎったり、窓の庇や、屋根の軒の出などによって、熱を取入れない工夫がされていました。(庇や軒の出は、ジメジメした梅雨時など、降雨時でも、窓が開けられるといった通風の利点も)
最近、敷地条件や騒音、防犯、都市部の過密など、住まいを取り巻く環境が悪くなり、どうしても、窓を閉めてクーラーをつけるといった設備に依存する住まいになるのは仕方がないかもしれませんが、住まいやそこに住む人の健康と言う点でも、もう少し先人達の知恵に敬意をはらいたいものです。