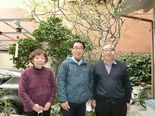元々障子とは、屋内の空間を仕切る建具の総称でした。襖や衝立も本来は障子。今日の桟に和紙を張った障子は、古くは明かり障子と呼ばれていました。
これらの障子(襖を含む)は日本独特のもの。欧米では引き戸はほとんどみられません。引き違いや引き戸は開け閉めに便利で、省スペース。すべて取り外せば大空間を造ることだって可能。
日本人の造った優れた建具です。お土産にもって帰る外国人もいるそうです。
障子の最も古い形は、奈良時代に誕生した衝立障子と言われています。
当時の貴族の家は今のワンルーム形式。目隠しの役目をする衝立障子は持ち運び可能で、今で言うフレキシブルな間取りを可能にしているのと同時に、絵画のキャンパスとして、室内の装飾品としての役割も担っていました。
平安時代の頃になると、現在の襖と呼ばれる建具が登場し、敷居と鴨居によって左右に開け閉めできるようになります。更に、鎌倉の頃になると格子状の桟の片面に和紙を貼った明かり障子が登場します。和紙を貼っただけなので光をよく通し室内の奥まで光を取り入れることが可能になりました。江戸時代以降、明かり障子は庶民の家の窓代わりとしても使われていくようになります。
障子を通しての柔らかな光りは、光と影の微妙な影を作り出し、日本人特有の繊細な美意識を育んだとも言われています。
小学校の林間学校でお寺に泊まった夜、レクリエーションでお坊さんが、障子の影を使って怪談話を盛り上げたのを、今でもおもいだします。お〜怖。