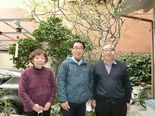お風呂には、もともと「湯」と「風呂」という2つの別々の意味があったそうです。
「湯」の語源は「斎川水(ゆかわみず)」という聖水のこと。古代の人々は身のケガレを清めるためにこの水をかぶりました。もちろん体のほこりや垢を落とすためだったのですが、ミソギの意味合いが強かったそうです。平安時代には貴族は湯殿にお湯を運ばせ、「湯浴み」といって、今の行水に近い入浴方法をとっていたそうです。
一方「風呂」の語源は穴ぐらを意味する「室(むろ)」がなまったもの、岩石を熱し、水をかけ蒸気を立たせて、敷物を敷いてその上に座り、汗をかいて疲れを癒す原始的なサウナ。奈良時代になると本格的な蒸し風呂施設が登場し寺院などで「施浴」とよばれ、庶民に振舞われたそうです。
江戸時代には寺院から独立し、庶民はお金を払って入浴するようになります。銭湯の始まりです。ここで、2つの入浴方法がひとつになり、現代の入浴方法が形造られたそうです。当時は基本的には男女混浴。そのために浴衣のようなものを着て入浴し、湯から上がれば2階の座敷でお茶のサービスや寿司が売られていたり、お花の稽古などが催され、庶民の娯楽兼社交場だったそうです。現代のスーパー銭湯みたいなものです。
江戸半ばになると「据え風呂」と呼ばれる内風呂が登場します。しかし、その当時「据え風呂」はかなりの贅沢品。据え風呂をもてない人は、持っている人のところに「もらい湯」をしたそうです。
温泉旅行の根強い人気に見られるように、日本人は老若男女を問わずお風呂好き。高温多湿の気候風土がその理由に挙げれますが、入浴の原点が「ミソギ」にあったように、日本人が風呂好きの理由は体だけでなく精神もリフレッシュしてくれることにあるのでしょう。
ちなみに私は昔ながらの銭湯が好きです。風呂上りに、スポーツ新聞を見ながら、缶ビールを「ぐびっと」
最高です。
お風呂のお手入れ
浴室の掃除は、汚れが蒸気でゆるんで落としやすくなっている入浴後が一番。3日に一度入浴した人が浴槽や壁、床、バス洋品など、湯をかけながらスポンジでサットとこすりおとします。あたたかいうちなら洗剤もいりません。そのあと、シャワーを使って浴室全体に水を流して湯気を取り、水気をとって終わりです。(カビなどの汚れを防ぐため、換気扇・窓を開けての乾燥が大事)
日頃の手入れをしっかりしていれば、洗剤を使うのは週に一度ぐらいで十分。